「タブレットを使って子どもに勉強させたいけれど、デメリットはないのかな?」と不安に思う保護者は多いです。タブレット学習はとても便利で、情報へのアクセスが容易ですが、いくつかのデメリットも存在します。
健康への悪影響や集中力の低下、自立性の低下が主な懸念事項です。しかし、デメリットを適切に対処する方法を知っていれば、タブレット学習を安心して取り入れられます。
この記事では、タブレット学習のデメリットを詳しく解説し、それぞれのデメリットを抑えるための具体的な対策を紹介します。記事を読んで、家族全員が安心してタブレット学習をできる方法を見つけてください。
タブレット学習のデメリット

タブレット学習には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットもあります。以下の3つが代表的なデメリットです。
- 健康への悪影響
- 集中力の低下
- 自立性の低下
タブレット学習のデメリットについて知り、対応策への理解を深めましょう。
健康への悪影響
タブレット使用時の姿勢は重要です。不適切な姿勢での使用は、首や背中への負担を大きくし、痛みの原因になります。長時間の同じ姿勢は筋肉を緊張させ、体の不調を引き起こします。
タブレットの画面から発せられるブルーライトにも要注意です。寝る前に使用すると、睡眠パターンを乱すことがあります。ブルーライトは体内のメラトニンの生産を抑制し、睡眠の質の低下につながります。
運動不足も見過ごせない問題です。長時間座ったままでのタブレット使用は、体を動かす機会を減少させるため、健康問題の原因となります。定期的な運動は健康を維持するために欠かせません。タブレットを使用する際には、健康リスクに注意が必要です。
集中力の低下

タブレットを使用した学習が集中力を低下させる原因は明らかです。タブレットには多くの誘惑があり、SNSやゲームなどへ簡単にアクセスできるため、気が散りやすいという問題があります。
画面からの連続的な刺激は短期間の集中は保てますが、長時間にわたる集中は困難です。画面を長時間見続けることで、目が疲れるため、集中力の低下につながります。
タブレットの使用は、忍耐力や持続的な集中力を育てるのには不向きです。デジタルでの学習内容に比べて、書籍で学ぶ場合の方が記憶に残りやすいという研究結果もあります。さまざまな要因が絡み合って、タブレット学習は集中力を低下させる可能性が高いと考えられます。
自立性の低下
タブレットを使った学習はとても便利ですが、子どもの自立性の低下につながるため要注意です。タブレットを使うことで、簡単に情報へアクセスでき、子どもから情報を探求する機会を奪ってしまいます。
子どもが問題に直面した場面で、自分で解決策を考える前に、すぐにインターネットで答えを検索してしまいます。問題解決能力の育成が阻害される可能性が高いです。親や教師が管理するアプリやシステムを使用することは、子どもの自主的に学ぶ意欲を低下させる懸念があります。
タブレットの即時フィードバックは便利ですが、依存してはいけません。自己判断や学習の進行管理のスキルが育ちにくくなります。タブレット学習はとても便利ですが、子どもの自立性を育てる上での課題も抱えています。
健康への悪影響を抑える方法
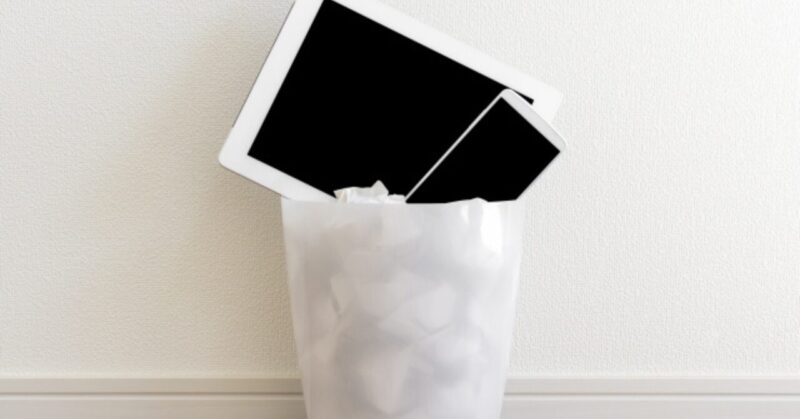
タブレット学習がもたらす健康への悪影響を抑えるためには、以下の対策を取ることが効果的です。
- 画面の明るさと距離を調整する
- 適切な学習時間を設定する
- 定期的に休息を入れる
- 運動習慣を取り入れる
対策を実施することで、タブレットを使う際に健康を守りながら、効率的に学習を進められます。
画面の明るさと距離を調整する
画面の明るさを環境に合わせて調整することは、目の疲労を減らすために効果的です。夜間や暗い部屋でタブレットを使用する際には、画面の明るさを下げることをおすすめします。目に優しく、長時間使用しても目の負担を軽減できます。
画面との適切な距離を保つことも、視力保護には重要です。画面から目までの距離は少なくとも30cm以上は離してください。適切な距離を保つことで、目への負担を減らし、姿勢の改善にもつながります。適切な対策を行うと、画面使用時の健康への悪影響を軽減することが可能です。
適切な学習時間を設定する

適切な学習時間を設定することは、子どもの健康と学習効果を最大化するために重要です。学習時間の設定には、子どもの年齢や注意力を考慮しなくてはいけません。
1回あたりの学習セッションは30〜50分が適切です。1日の合計学習時間は小学生なら1〜2時間、中学生以上なら2〜4時間がおすすめです。週に3〜4日の学習を行い、セッション間には10〜15分の休憩を挟むことが効果的です。
子どもの集中力が高い時間帯に利用しましょう。学校から帰宅してすぐの時間がおすすめです。計画的に学習時間を設定すると、学習の質を保ちながら、子どもの健康も守ることが可能です。
定期的に休憩を入れる
定期的に休憩を取ることは、学習の効果を高めるために必要です。長時間の学習による疲れを防ぐため、50分の学習をした後には、10分程度の休憩を取るようにします。
休憩時間は、目を休めるために視線を遠くに向けたり、短いストレッチや軽い運動で体の緊張を解消したりしてください。休憩中に5分程度の体操やウォーキングが効果的です。リフレッシュに効果的な時間の使い方をしましょう。
休憩時間にカフェインや糖分が高い飲食を避け、水分補給を心がけることも大切です。休憩を忘れないようにスケジュールに組み込み、アラームを設定することが効率的な学習に役立ちます。
運動習慣を取り入れる
外での活動を取り入れることは、タブレット学習のデメリットを軽減するために効果的です。毎日の生活において、定期的な運動習慣を持つことも大切です。
自然の中で遊ぶ時間や、スポーツをする時間を設けることで、心身のリフレッシュが図れます。外での活動は、健康の維持や社会性の育成にもつながります。
集中力の低下を抑える方法

タブレット学習において集中力の低下を抑える方法は、以下の3つです。
- タイマーを使って時間管理をする
- 学習環境を整備する
- 目的に応じてアプリを使い分ける
実践すると、集中力を保ちながら効率的に学習を進められるようになります。
タイマーを使って時間管理をする
タイマーを使って時間管理をすることは、集中力を高め、効率的に学習を進めるために有効です。タイマーを設定することで、決められた時間内に集中して作業ができます。
25分間集中して学習した後に5分間の休憩を取る「ポモドーロテクニック」がおすすめです。短い時間で集中することを繰り返すため、長時間の勉強で疲れてしまうことを防ぎながら、効率的に学習できます。
慣れてきたら、少しずつ学習時間を延ばすことも考慮しましょう。最初は25分学習して5分休憩を取ることから始め、次第に45分学習して10分休憩を取るように調整します。適度なチャレンジを取り入れることで、集中力を鍛えられます。
タイマーを使って日々の学習時間を記録して管理することも可能です。どれだけ勉強したかを見えるようにすることで、規則正しい学習につながります。タイマーを活用し、学習の質を向上させましょう。
学習環境を整備する
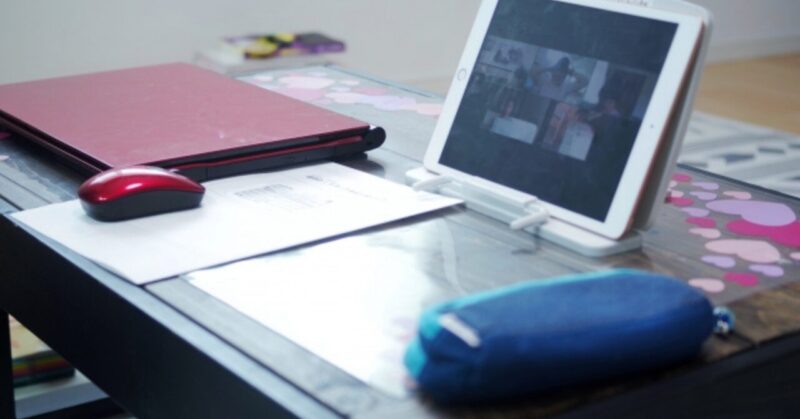
学習環境を整備することで、集中力と学習効率を高められます。整えられた環境は、学習へのモチベーションを向上させる効果があります。
騒音や雑音が少ない場所で学習することが大切です。家庭内で学習スペースを確保する際は、できるだけ静かな場所を選んでください。図書館や自習室など、集中しやすい環境を利用することも効果的です。
学習環境の整備方法としては、快適な椅子と机を用意することから始めてください。長時間の学習でも体にかかる負担を軽減できます。自然光を取り入れ、適切な照明を確保することで、目の疲れを軽減します。学習用具は整理整頓して、必要なものを手の届く場所に置いてください。スムーズに学習が行えます。
学習中はSNSやゲームアプリなどの通知をオフにすることが大切です。アプリの通知が頻繁に来ると、気が散りやすくなります。学習専用のデバイスやアプリを利用することで、学習に集中できます。
目的に応じてアプリを使い分ける
アプリを目的に応じて使い分けることは重要です。数学を学ぶ際には数学専用のアプリを使うと、科目に特化した問題や解説が得られ、理解が深まります。言語学習には語学学習専用のアプリを使用することで、音声認識や単語テストなど、言語習得に役立つ機能をフル活用できます。
目的以外の機能が少ないシンプルなアプリを選ぶことで、余計な機能に惑わされることなく、学習への集中が可能です。必要な機能だけを使いこなし、学習効果を最大限に引き出しましょう。
複数のアプリを組み合わせて使用することも良い方法です。視覚的な学習を助けるアプリと、音声による学習アプリを同時に利用することで、多角的なアプローチにより理解が深まります。
自立性の低下を防止する方法
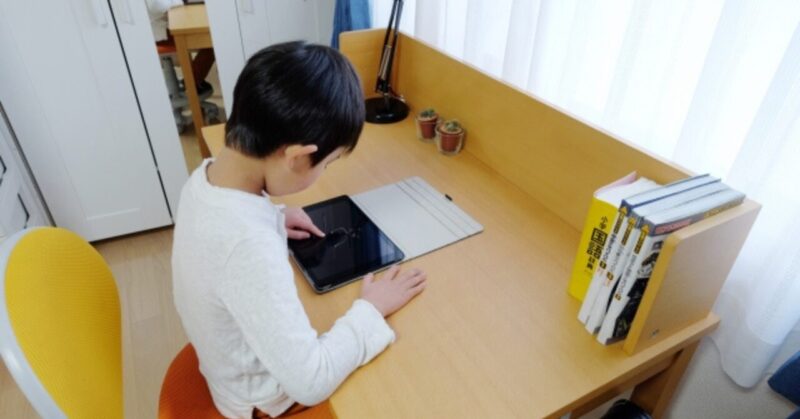
自立性の低下を防ぐためには、正しいプロセスが必要です。以下のステップで自立性を高めます。
- 目標を設定する
- 自己評価をする
- 定期的にフィードバックする
子どもは困難に直面した際に、自分で解決策を見つけ、乗り越える力を身に付けます。日々の活動を自分で管理することで、学習に対する責任感を育て、自立へとつなげてください。
目標を設定する
目標を設定することは、自立性を高め、学習効果を最大限に引き出すために重要です。学習の目的に関連した測定可能な目標を設定してください。
短期目標と長期目標を設けて、目標達成のためのステップを明確にします。定期的に進捗を確認し、必要に応じて調整しなくてはいけません。目標が達成できれば次のステップへ、未達の場合は学習方法やスケジュールを見直します。
自己評価をする

タブレット学習において、自己評価を行うことは自立性を高めるために重要です。学習の進捗を定期的に確認することで、自分の学習状況を把握できます。自分の強みと弱みを明確にできるので、今後の勉強の計画を正しく立てられます。
自己評価では、学習目標に対する結果を振り返ってください。数学の単元を理解することを目標としていた場合、関連するテスト結果や解説を用いて、理解できているかを評価します。次の学習に進む前に、追加のテストや必要な復習のポイントがわかります。
自己評価はモチベーションの維持にも効果的です。自分の成長を定期的に確認することで、学習への意欲が向上し、自立した学習態度が育まれます。自己評価を習慣化することで、自己管理能力が向上し、学習に対する自信も高まります。
定期的にフィードバックする
学習する上で、定期的にフィードバックを行うことは欠かせません。自分の学習進度を把握し、モチベーションを維持するためにも必要な作業です。フィードバックは、学習者の反省と成長をする手段として最適です。
フィードバックの方法は、教師や親が定期的に子どもの学習状況を確認し、励ましの言葉や改善策を伝えます。フィードバックを受けた子どもは、学習に対する自信を高め、次のステップに向かって努力するきっかけになります。
フィードバックを通じて、自分が達成した成功体験を思い出すことが可能です。成功体験があることで、新たな学習への動機となります。定期的なフィードバックを通じて、自立して学習できる習慣を手に入れましょう。
» 小学生向けのタブレット学習教材を解説
まとめ

タブレット学習は上手く活用できれば便利ですが、健康への悪影響、集中力の低下、自立性の低下といったデメリットが存在します。デメリットの影響を抑えるための方法を知り、タブレット学習を取り入れることが大切です。
画面の明るさを調整したり、適切な距離で使用したりすることで、目への負担を減らせます。タイマーを使って時間管理を行い、定期的に休憩を取ると、集中力を維持することが可能です。
目標を設定し自己評価を行うことで、自立性を高められます。定期的にフィードバックを行い、学習の進捗を伝えましょう。学習での成功体験を積むことで、自立性と学習意欲が高まります。
デメリットを抑える方法を実践すると、タブレット学習の効果を最大限に引き出すことが可能です。普段の学習にタブレットを取り入れて、学習効果を高めましょう。
» 小学生の通信教育について解説